ジャズ・フルートは、その自由なアドリブと、息遣いが感じられる音色に、多くの人が惹かれますね。
クラシック音楽でのフルートとはまた違った魅力があり、どう違うのかや、その特有の奏法も気になるところです。
ジャズ・フルートの歴史を彩ってきた名手たちや、特に有名な日本人奏者にはどんな人がいるのでしょうか。
これから始めたい初心者にとっては、楽器の選び方や、最大の難関とも思えるアドリブ練習の具体的な方法、独学に役立つ教則本や楽譜についても知りたいところです。
また、東京近辺で通える良い教室やレッスン、さらには練習の成果を試せるジャムセッションに参加できる場所があるのかどうかも、重要なポイントだと考えられます。
もちろん、まずは聴いてみたい定番曲や名盤の情報も欠かせません。
この記事では、ジャズ・フルートに関するこうした疑問を一つひとつ掘り下げ、その魅力と具体的な始め方について、私なりに集めた情報をまとめていきます。
- ジャズ・フルートの歴史や代表的な名手
- クラシック演奏とは異なる特有の奏法
- 初心者向けの楽器選びとアドリブ練習法
- 東京で学べる教室やセッション情報
ジャズ・フルートの魅力と基本

まず、ジャズ・フルートがどのように発展してきたのか、その歴史や代表的なプレイヤー、そしてクラシック演奏とは何が違うのか、基本的な魅力を掘り下げていきます。
この楽器の「らしさ」がどこにあるのかが見えてくるはずです。
ジャズ・フルートの歴史と名手たち
ジャズ・フルートがソロ楽器として確立されたのは、1950年代に入ってからだと言われています。
それ以前もアンサンブルで使われることはありましたが、音量の問題もあり、トランペットやサックスのように前面に出る楽器ではありませんでした。
流れが変わったのは、ビバップの熱狂が落ち着き、リラックスした「クール・ジャズ」が好まれ始めた時期です。
フルートの持つリリカルな音色が、この新しいジャズのスタイルと非常に相性が良かったわけですね。
この時代に登場したパイオニアたちが、ジャズ・フルートの可能性を切り開きました。
サム・モストは、ビバップの複雑なフレーズをフルートで演奏する技術的な基盤を築いた一人です。
バディ・コレットは、ウエストコースト・ジャズのシーンで、アンサンブル内でのフルートの新しい役割を示しました。
そして、ジャズ・フルートをポピュラー音楽の領域にまで押し上げた最重要人物が、ハービー・マン (Herbie Mann) です。
彼はR&Bやソウル、ラテンといった多様なジャンルを取り入れ、ジャズの枠を超えた幅広いリスナーを獲得しました。
他にも、前衛的なアプローチで後世に大きな影響を与えたエリック・ドルフィー (Eric Dolphy) や、クラシックの素養に裏打ちされた完璧なテクニックを持つヒューバート・ロウズ (Hubert Laws) など、多くの名手たちがこの楽器の表現を深めてきました。
有名な日本人ジャズ・フルート奏者
日本国内でも、ジャズ・フルートは独自の発展を遂げており、多様なスタイルの素晴らしい奏者が活躍しています。
例えば、カリブ海と日本を拠点に活動し、「カリビアンフルートの第一人者」として知られる赤木りえ氏は、その華やかでリズミカルな演奏が魅力的です。
また、ボストンで本格的にジャズを学び、都内を中心に活動する酒井麻生代氏や、国立音楽大学出身の波戸崎操氏など、クラシックの確かな技術をベースに持ちながら、ジャズのフィールドで活躍する実力派も多くいらっしゃいます。
サックスとフルートを両方演奏する小林香織氏のように、フュージョンやポップスの分野で活躍する奏者もいれば、ボサノヴァを中心に活動する紺野紀子氏のような方もいて、一口に「日本のジャズ・フルート奏者」と言っても、そのスタイルは非常に多彩です。
クラシックとの違い、特有の奏法
同じフルートという楽器を使いますが、ジャズとクラシックでは目指す音楽表現が根本的に異なります。
決定的な違い
- アドリブ(即興演奏)
これが最大の違いですね。クラシックが楽譜の忠実な再現性を追求するのに対し、ジャズはコード進行という設計図の上で、その場でメロディを創造するアドリブが核となります。 - 音色(トーン)
クラシックが均一で透明感のある音色を理想とするのに対し、ジャズはより個性的です。意図的に息の音を多く含ませる「サブトーン」や「エアリーサウンド」を使い、人間の「声」に近い生々しい表現が好まれます。 - ビブラート
クラシックでは均一なビブラートが求められることが多いですが、ジャズでは表現に応じて全くかけない「ノン・ビブラート」から、感情的な激しいビブラートまで、幅広く使い分けます。 - リズム解釈
ジャズの基本は「スウィング」と呼ばれる独特の跳ねたリズムです。楽譜上は同じ長さの8分音符でも、実際には「タッカタッカ」という3連符のようなリズムで演奏されます。
ジャズ特有の奏法
- メロディ・フェイク (Melody Fake)
アドリブへの第一歩です。元のメロディをそのまま吹くのではなく、リズムを変えたり装飾音を加えたりして、意図的に「崩して」演奏するテクニックです。 - ベンド (Pitch Bend)
音程を意図的に揺らしたり、しゃくり上げたり(グリスアップ)、しゃくり下げたり(フォールダウン)する奏法。ブルースのフィーリングを出すために多用されます。 - ゴーストノート (Ghost Note)
聴こえるか聴こえないか程度の小さな音をフレーズの合間に入れ、リズムの「ノリ(グルーヴ)」を生み出す高度なテクニックです。 - タンギング (Tonguing)
クラシックの「Tu(トゥ)」という明確な発音より、「Du(ドゥ)」という柔らかい発音(レガート・タンギング)が好まれます。
おすすめの名盤と定番曲
ジャズ・フルートの魅力を知るには、まず代表的な曲やアルバムに触れるのが一番です。
はじめの一歩
まずは、ジャズ・フルートで演奏される機会が多い、聴きやすいスタンダード曲から入るのがおすすめです。
- Black Orpheus (黒いオルフェ)
ボサノヴァの名曲で、フルートのメランコリックな音色が非常によく合います。 - One Note Samba (ワン・ノート・サンバ)
同じくボサノヴァの定番曲です。 - Fly Me to the Moon
ジャズ・スタンダードの代表曲ですね。
押さえておきたい名盤
- Herbie Mann 『Memphis Underground』
ハービー・マンによる、ジャズ、ソウル、R&Bが融合した歴史的名盤です。フルートがこんなにファンキー(ノリが良い)な楽器だったのかと驚かされます。入門盤として最適だと考えられます。 - Eric Dolphy 『Out to Lunch!』
モダンジャズの重要作の一つ。伝統的なジャズの枠を超えた、前衛的でスリリングなフルート演奏が聴けます。 - Hubert Laws 『The Rite of Spring』
クラシックの名曲「春の祭典」をジャズ・クロスオーバーとして演奏したアルバム。ヒューバート・ロウズの完璧なテクニックに圧倒されます。
ジャズ・フルートの始め方と練習

ここでは、実際にジャズ・フルートを始めるための具体的なステップ、楽器の選び方からアドリブの練習法、そして学べる場所について詳しく見ていきましょう。
初心者向け楽器の選び方
ジャズを演奏する場合、クラシックとは楽器に求められる特性が少し異なります。
クラシック、特にオーケストラでは、明るく輝かしい、アンサンブルの中で際立つ「音抜けの良さ」が重視されることが多いです。
一方、ジャズやポップスでは、マイクで音を拾う前提はありつつも、ドラムやベース、ピアノといった大音量の楽器とアンサンブルを組む必要があります。
そのため、単に明るい音色よりも、息を強く吹き込んでも音が痩せない「パワー感」や、中低音域の「渋さ」、そして「重みのある音色」が好まれる傾向があるようです。
この観点で国内メーカーを比較すると、面白い特徴が見えてきます。
- ヤマハ (YAMAHA)
音抜けが良く明るい、芯のある音色が特徴です。バランスが良く万能で、吹奏楽などで高く評価されています。音が出しやすく耐久性も高いので、初心者にも安心です。 - パール (Pearl)
優しく柔らかく、上品な音色が特徴です。オーケストラ向きと評されることもあり、パワフルさよりも楽に音を出したい人に向いているかもしれません。 - ムラマツ (Muramatsu)
伝統的にプロ向けのメーカーとして知られ、重厚感があり、渋さや重みのある音色が特徴とされます。低音が出やすく、パワーと音の存在感に優れると評価されており、この点がジャズやポップス奏者にムラマツが推奨される理由だと考えられます。
とはいえ、これらはあくまで一般的な傾向です。
特に初心者向けのモデル(ムラマツの「EX」モデルなど)は、どのメーカーも高品質で吹きやすく作られています。
一番大切なのは、実際に楽器店で試奏してみて、自分が「この音色が好きだ」「これが吹きやすい」と感じる楽器を選ぶことです。
可能であれば、経験者や楽器店の店員さんに相談しながら選ぶことをおすすめします。
アドリブ練習の具体的なステップ
ジャズ・フルートを始める上で最大の壁が「アドリブ」ですね。
しかし、その概念を正しく理解すれば、心理的ハードルはかなり下がると私は思います。
アドリブへのマインドセット
多くの初心者は、アドリブを「全くの無から有を生み出す魔法」のように捉えがちですが、それは誤解です。
アドリブは、日常の「会話」に非常に近いと考えられます。
私たちは会話をするとき、単語や文法を一から発明しているわけではなく、これまでに「覚えた単語やフレーズ」を無意識のうちに組み合わせて「応用」しています。
ジャズのアドリブも同じで、まずは先人たちが作り上げた「フレーズ(リック)」を学び、それを自分なりに応用することから始まります。
具体的な練習ステップ
- メロディ・フェイクから始める
いきなりソロを演奏しようとせず、まずは知っている曲のメロディを少し崩してみる「メロディ・フェイク」から始めるのが、最も安全で効果的な第一歩です。 - 得意なフレーズを覚える
教則本や好きな奏者の真似で良いので、短い(2小節程度)「カッコいい」と感じるフレーズをいくつか暗記します。これが会話における「単語」になります。 - リズムを変化させる
覚えたフレーズを、スウィングのリズムに乗せたり、音符の長さを変えたり、リズムをわざとずらしたり(シンコペーション)する。これだけで、一つのフレーズが何通りものバリエーションに生まれ変わります。 - 音階の順番を入れ替える
フレーズ内で使われている音の順番を入れ替えるだけでも、新しいフレーズが生まれます。 - 短いフレーズを繋ぐ
最初は2小節程度の短いフレーズを繋ぎ合わせることから始め、徐々に長くしていきます。
理論的アプローチ
感覚だけに頼らず、理論で補強することも重要です。
- コードトーン(和音の構成音)
アドリブの「骨格」となる最も重要な音です。曲のコード進行に合わせて、このコードトーンを中心に演奏すれば、大きく音が「外れた」と感じることはありません。 - スケール(音階)
コードトーンの間を埋める「装飾」の音です。まずは基本となる「メジャースケール」の習得が鍵となります。
独学に役立つ教則本と楽譜
アドリブの基礎体力やフレーズ(リック)を学ぶためには、優れた教則本が不可欠です。
レベル別おすすめ教則本
- 【初級編】イージー・ジャズ・コンセプション
人気の「ジャズ・コンセプション」シリーズの初級編です。平易な素材でジャズらしいアドリブの基礎を学べます。 - 【初級編】はじめてのジャズとアドリブ入門
まさにジャズ演奏の「基本のき」を学ぶための一冊です。 - 【脱初心者】脱初心者!管楽器プレイヤーのためのジャズ・ハノン
クラシックの基礎練習(ハノン)のジャズ版。「ジャズらしさ」を身につけるための基礎練習が詰まっています。 - 【中・上級編】ジャズ・コンセプション
アドリブを学ぶための王道のエチュード(練習曲)集。付属のマイナスワンCD(伴奏カラオケ)の質も高いと評判です。
ジャズの理論や歴史をさらに深く学びたい場合は、専門書を読んでみるのも良い方法です。
こちらの記事もおすすめです
ジャズの理論書、歴史書、入門書など、目的に合わせたおすすめの書籍を紹介しています。
独学の助けになる一冊が見つかるかもしれません。
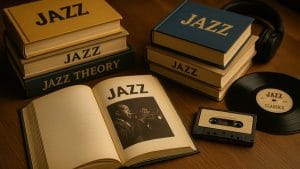
おすすめ楽譜集
基礎を学んだ後は、具体的な曲を演奏するための楽譜集が必要になります。
特に全音楽譜出版社から出版されている「フルートで奏でる」シリーズ(湯川徹 編曲)は、ジャズ・アレンジの質が高く、ピアノ伴奏譜と伴奏CDが付属しているため、独習や発表会に最適とされています。
- フルートで奏でるジャズ・メロディー(定番スタンダード曲)
- フルートで奏でるシネマinジャズ(映画音楽)
- フルートで奏でるボサノヴァ(ボサノヴァ定番曲)
など、様々なジャンルの楽譜集が出版されています。
ジャズ・フルート教室とレッスン
独学も可能ですが、やはり専門家から体系的に学ぶのが上達への近道です。
特にジャズ特有のリズム感やアーティキュレーション(奏法)は、直接指導を受けることで効率よく習得できると考えられます。
東京の主要エリア(新宿、渋谷など)には、ジャズ・フルート・コースを提供する音楽教室が複数あります。
教室選びのポイント
- レッスン形式
専門家と1対1で学べる「個人レッスン」か、仲間と学べる「グループレッスン」か。自分のペースで学びたいなら個人、アンサンブルも楽しみたいならグループが良いかもしれません。 - サポート
楽器無料プレゼントや無料体験レッスンの有無も確認したいポイントです。 - 立地
結局のところ、通いやすさは長続きの秘訣です。
また、第2部で紹介したような現役のプロ奏者が、個別にプライベートレッスン(定期的または不定期)を提供しているケースもあります。
特定の奏者のスタイルを学びたい場合は、そうした情報を探してみるのも良いでしょう。
東京でセッションに参加できる場所
教室でインプットした知識をアウトプットする「実践の場」が、ジャズの学習には不可欠です。
それが「ジャムセッション」です。
ジャムセッションとは、ミュージシャンが特定の店やスタジオに集まり、スタンダード曲などを題材に即興的に合奏する場を指します。
とはいえ、いきなり上級者ばかりのセッションに飛び込むのは非常にハードルが高いですよね。
そこでおすすめなのが、「ジャムセッション初心者」を対象としたワークショップや練習会です。
例えば、東京・錦糸町にある「J-flow」というジャズカフェ(バー)は、「ジャムセッション初心者」を対象としたワークショップ講座や練習会サークルをほぼ毎日開催していることで知られています。
プロの演奏家と共にアドリブを学ぶワークショップなども定期的に行われており、フルート奏者も含む楽器全般を対象とした講座が充実しているようです。
教室で基礎を固め、こうしたセッションの場で実践経験を積む、というのが王道の上達ルートと言えそうですね。
ジャムセッションには、参加費(ミュージック・チャージ)や飲食代が別途必要となるのが一般的です。また、初心者向けセッションであっても、基本的なコード進行の理解や、演奏したい曲の譜面(黒本)を準備しておくといった最低限のマナーが求められる場合があります。

ジャズ・フルートを探求しよう

この記事では、ジャズ・フルートの魅力から具体的な練習法まで、幅広く情報をまとめてきました。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
- ジャズ・フルートの核はアドリブ(即興演奏)にある
- クラシックとは音色、ビブラート、リズム解釈が根本的に異なる
- ジャズ特有の奏法にはサブトーンやベンドがある
- 歴史は1950年代のクール・ジャズと共に発展した
- パイオニアはサム・モストやバディ・コレット
- ハービー・マンがジャズ・フルートを大衆化させた
- エリック・ドルフィーは前衛的な演奏で影響を与えた
- 日本人奏者も赤木りえ氏など多彩なスタイルで活躍している
- 名盤の入門編はハービー・マン『Memphis Underground』
- 定番曲は「黒いオルフェ」などのボサノヴァとも相性が良い
- ジャズ向きの楽器はパワーや重みのある音色が好まれる傾向
- メーカーではムラマツがジャズ奏者に好まれる傾向がある
- 楽器選びは試奏して決めることが最も重要
- アドリブは「会話」と同じで、フレーズを覚えて応用することから始まる
- アドリブ練習はメロディ・フェイクから始めるのが安全
- 理論学習ではコードトーンの理解が骨格となる
- 独学には「ジャズ・コンセプション」などの教則本が役立つ
- 上達には教室での体系的な学習が効率的
- 実践の場としてジャムセッションが重要
- 東京には「J-flow」のような初心者向けセッションの場がある









